坂戸、川越で土地を売却する時の注意点、境界明示義務とは 不動産売却コラム |センチュリー21クレド
土地を売却する時の注意点、境界明示義務とは
「境界明示義務とは?」「境界の明示を確認するには?」土地の売却を検討している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では土地を売却する際の境界明示義務と明示の確認方法について紹介しています。この記事を読めば、土地を売却する際に境界が確定していないことによって起こりえるトラブルについて網羅できますので、是非ご一読ください。
そこで、今回の記事では土地を売却する際の境界明示義務と明示の確認方法について紹介しています。この記事を読めば、土地を売却する際に境界が確定していないことによって起こりえるトラブルについて網羅できますので、是非ご一読ください。
目次
境界の明示とは

境界の明示は、土地売買において売主が買主に対して明確に土地の境界を示すことを指します。これは「境界明示義務」と呼ばれ、土地取引において不可欠です。売主が境界を明確に示さない場合、買主と隣接地所有者との間で問題が生じる可能性があります。したがって、買主の信頼を確保するため、法的にも境界の明示は求められています。
境界をはっきり示すために使用されるのは、境界標やブロック塀、金属プレートなどです。ただし、これは専門の土地家屋調査士などの資格を持つ人々が設置するものです。土地所有者や隣接地所有者も立ち会いをして境界の確定を行なった後は、筆界確認書と呼ばれる書類が作成され、売主は不動産会社を通じてこれを提出します。これにより、買主が購入後に境界に関するトラブルを心配することなく、安心して土地を取得できる仕組みが整備されています。
境界確定
境界確定には「地番」と呼ばれる土地の番号が用いられます。この地番は土地登記簿に必要な情報で、隣接地との境目を示します。境界が不明瞭だと、問題が生じる可能性があるため注意が必要です。2006年に導入された「筆界特定制度」は、境界を特定する新たな方法です。当事者はトラブル解決のために申請し、特定登記官が筆界調査員に調査を依頼し境界を確定します。この制度により、国が明確な境界を定めるため、問題解決が迅速に行われ、土地取引における信頼性とトラブルの未然防止が向上します。
境界確認
境界確認は不動産の購入時に欠かせない重要なポイントです。売主が境界確定訴訟中であっても、その事実を隠して売買を行うことを防ぐために義務付けられています。境界確認の際には、隣接する全所有者が集まり確定測量が行われます。この測量作業は土地家屋調査士によって行われ、公道に接している場合は官民境界査定員も関与することがあります。確定測量後には筆界確認書が作成され、関係者の実印が押されます。
これらの手続きにより、将来的な境界に関するトラブルを未然に防ぐ効果が期待されます。買い手にとっては、購入後の安心感と不動産取引の透明性が確保されることにつながるでしょう。
境界の明示がない場合に起こりえるトラブル
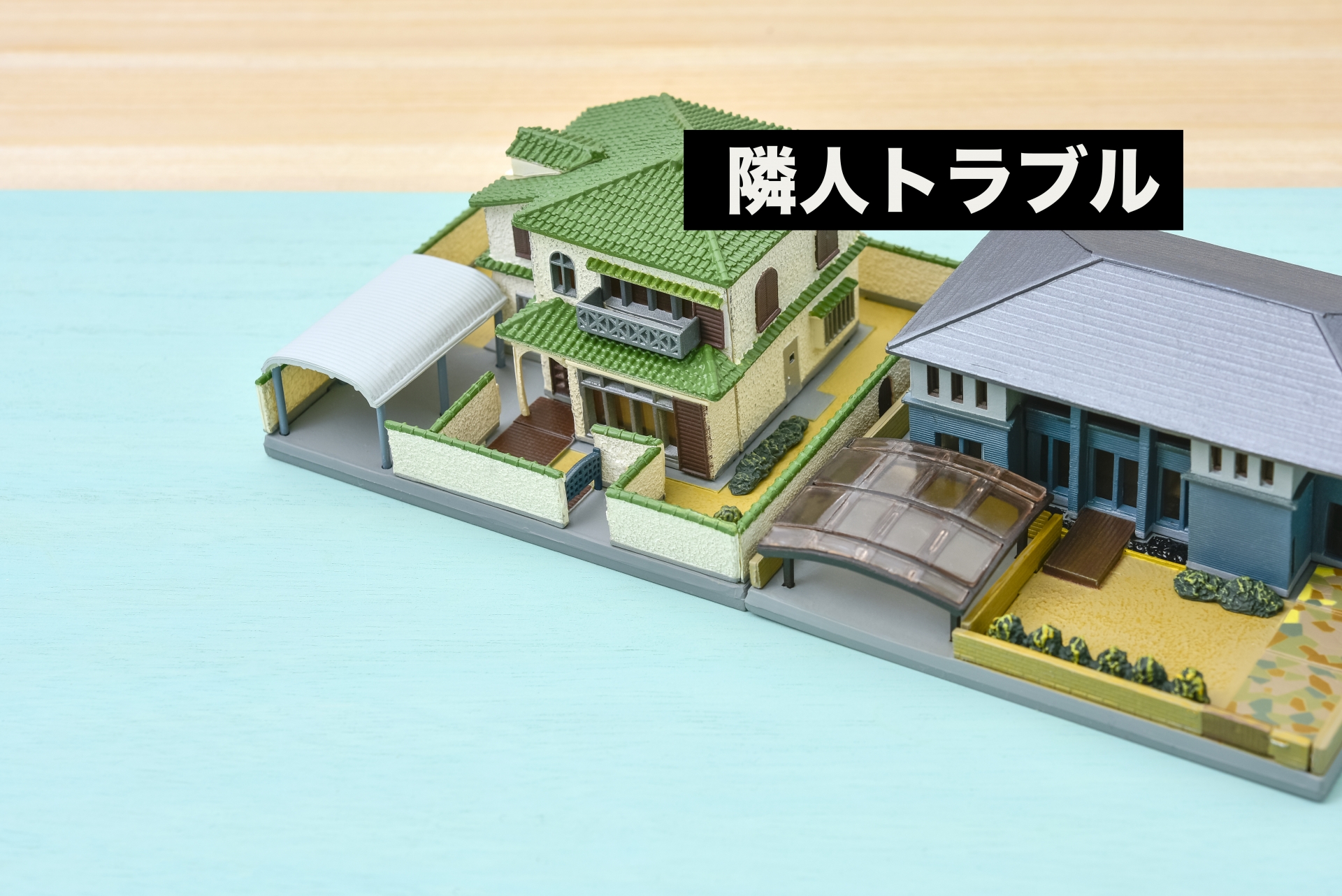
土地を売却する際、境界の明示は非常に重要な要素です。境界が明示されていない場合、さまざまな問題が生じるリスクが高まります。特に、買主との間に誤解や紛争が発生する可能性が増大します。ここでは、境界が明示されていないときに生じるトラブルの具体例について詳しく見ていきましょう。
建物や塀などが越境している
「越境」とは、自分の土地内に他人の所有物が侵入する状態を指します。例えば、隣地の上空に建物がかかっていたり、庭木や枝が隣地に出ている場合が挙げられます。地下に埋まった管や線も越境の一例です。このような越境があると、トラブルの原因となる可能性が高まります。新たな建築物を建てる際や土地を売却する際にも問題が生じる要因となるため注意が必要です。この問題を解決するためには、隣接地の所有者と協力して越境部分を確認し、合意を取ることが重要です。具体的には、専門の測量士を利用して境界を明確に定め、境界標を設置することで問題を未然に防ぐことができます。立ち会いを行うことで両当事者の合意が得られ、売買や新築時におけるトラブルを防ぐことができます。
近隣の所有者が境界確定に同意しない
境界を確定するには、隣地の所有者の協力が欠かせませんが、中には同意を得るのが難しいケースもあります。特に昔からの主張や意見の違いがトラブルの要因となることがよくあります。また、共同所有の場合、全員が同意しなければならないケースもあるでしょう。このような状況では、隣地所有者との話し合いを通じて各々の立場や懸念を明確に理解することが大切です。昔からの主張や意見の違いがある場合は、過去の文書や資料を引き合いに出し、合理的な解決策を模索します。
共同所有の場合、全員の合意を得ることは難しいかもしれませんが、各所有者の意見を尊重し、妥協案を見つけることが重要です。仲介者や専門家のアドバイスを受けつつ、公平な解決策を探り、相手の立場を理解して共感を示すことで、トラブルを回避した円滑な境界確定を実現することができるでしょう。
所有者が死亡している
先述した通り、境界確定には隣地の所有者の協力が欠かせませんが、所有者が亡くなっているケースもあるでしょう。この場合、相続人が代わりに協力し、境界の確認作業を進めることになります。相続人が複数人いる場合は調整が難しいこともあるかもしれませんが、話し合いによって同意を得る必要があります。相続人が複数人いる場合、互いの意見が分かれることもあるかもしれません。しかし、透明性を保ちつつ、相互の立場を理解し合うことで合意に近づくでしょう。仲介者や専門家の助言を受けながら、折衷案を模索し、合意形成を図ることが大切です。
想定より土地の面積が小さい
土地の購入時、契約書に示される土地の広さと、実際の測量結果が異なることがあります。登記簿上の広さと実測の差異は一般的です。しかし、大きな差が生じる場合、トラブルの引き金になる可能性があるため、実際の測量による確認は極めて重要です。購入前に、土地の契約書で示される広さを確認するのはもちろんのこと、専門の測量士による実地測量も実施しましょう。測量士は正確な計測を行い、土地の実際の広さを明らかにします。このような手続きによって、登記簿と実測結果との一致を確認し、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
特に土地の境界や隣地との関係性を確認するために、正確な測量は不可欠です。購入後に広さの違いが発覚すると、隣地所有者との争いや建設計画の変更などの混乱を招く可能性があります。購入前の段階で正確な情報を得ることで、スムーズな不動産取引が行なえるでしょう。
境界の明示を確認する方法

土地の売却を検討する際、境界を正確に確認することは避けては通れません。境界の明示が正確であれば、トラブルのリスクを大きく低減させることができます。しかし、実際にどのように境界の明示を確認すれば良いのか気になる人もいるのではないでしょうか。ここでは、境界の明示を確実に行うための具体的な手段を解説します。
測量図を確認する
土地の測量図があれば、境界がどこにあるか確認できます。ただし、測量図の種類によっては隣地所有者との合意が得られていない場合もあるので注意が必要です。測量図は主に3種類あります。確定測量図
確定測量図は、隣地所有者全員の立会いを得て境界が確定された図面です。確定測量図は民間査定や官民査定などすべての手続きを経て作成されるため、境界の明示に用いる際には最適です。確定測量図を使うことで、土地や物件の境界が正確に示され所有権の確認が容易になります。
購入者も確定測量図のある物件を求めることが一般的です。そのため、土地を売る際には確定測量図の準備が重要です。確定測量図があると、購入者は物件の境界や隣地との関係を明確に理解し、将来のトラブルを避けられると感じるでしょう。
売主としては、土地の売却に際して確定測量図を用意し、購入者にとっても安心感を提供することが大切です。円滑な取引と信頼性を確保するために、確定測量図の利用を検討することをおすすめします。
現況測量図
現況測量図は、確定測量図以外の実測図を指します。確定測量図に次ぐ信頼性を持つのが現況測量図で、隣地所有者の立会いのもとで作成される実測図です。現況測量図は確定測量図と比べて官民境界の確定を省いた図面を含みます。
ただし、現況測量図には隣地境界の立会いなしに測量された図面も存在します。したがって、現況測量図を選ぶ際には注意が必要です。確実な情報を得るためには筆界確認書が必要です。この書類は双方の所有者が実印で押印したもので、測量の立会いがあったかどうかを示しています。
購入者側も、確かな信頼性を持つ現況測量図を選ぶ際には、この「筆界確認書」の有無を確認することが大切です。これによって、境界に関する紛争やトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
地積測量図
地積測量図は、分筆登記などの際に登記所に提出される測量図です。古い図面には注意が必要で、特に平成17年以前の地積測量図は隣地所有者との立会いがないまま作成されたものが多いため、境界が確定していないことが多いです。
地積測量図を利用する際には、その信頼性に注意が必要で、立会いが行われているかどうかを確認しましょう。隣地所有者との立会いがあった図面であれば、境界がより正確に示されている可能性が高く、信頼性があります。一方で、立会いのない古い地積測量図は、境界確定において信憑性に欠ける可能性もあります。
地積測量図を活用する際は、可能な限り隣地所有者との立会いが行われた図面を選ぶことがおすすめです。境界の正確な位置を把握し、将来のトラブルを避けるためには、信頼性の高い測量図を使用することが大切です。
境界標を確認する
境界を明確にするためには、境界標が存在していることが不可欠です。確定測量図があるとしても、境界を明示するには境界標がきちんと残存していることが重要です。金属プレートなどの境界標は、長い年月の経過で紛失することがあります。境界標が失われている場合、隣地所有者との合意のもとで再度境界標を設置する必要があります。この過程においては、正確な境界を示すために、測量士などの専門家への依頼が必要です。
境界標が残っている状態であれば、土地の所有権や隣地との関係性を明確に示すことができます。これにより、土地売買や新築などの際に、境界に関する紛争を未然に防ぐことができるでしょう。境界標の重要性を理解し、適切な手続きと専門家の助けを借りて、境界を明確にすることが大切です。
マンションは境界確定されているケースも
境界が確定しているマンションの場合、境界明示の必要はありません。マンションの売却においては、マンションデベロッパーが開発用地を購入する段階で既に境界が確定していることが一般的です。マンションの売主には、境界明示義務が発生せず、契約書にも境界明示に関する条文は通常記載されません。開発用地の境界がデベロッパーによって事前に確認されており、各戸が区画される際にも境界は既に設定されています。
したがって、マンションの売主は通常境界明示に関する特別な対応は必要ありません。マンションの購入者は、デベロッパーが設定した境界に基づいて取引を行うため、境界に関する問題は起こりにくいです。ただし、特殊な事情がある場合には、法律や契約書に基づいた専門家の助言を得るようにしましょう。
境界明示の確認できない場合の対処法
境界明示の証拠が不足している場合、境界確定の手続きが必要です。不動産の売買契約において、売主は物件を完全な状態で引き渡す義務があります。境界標が紛失している場合、再度復旧させる必要があります。また、測量図や境界標が存在しない状況でも、境界確定を行うことが必要です。境界明示が曖昧な状態では、将来的なトラブルを防ぐためにも境界確定が重要です。測量士や土地家屋調査士などの専門家によって境界を再度明確に測量し、境界標を設置することで、所有権の確定や隣地との関係性を明確にすることができます。これにより、購入者と売主の双方が不安を感じることなく取引を進めることができるでしょう。
売主には、境界確定の手続きを適切に行い、物件の引き渡しを円滑に行うことが求められます。購入者としては、境界確定が行われていることを確認し、将来のトラブルを予防するためにも注意深く取引を進める必要があります。
まとめ
今回の記事では、土地を売却する際の境界明示義務と明示の確認方法を紹介しました。境界の明示がない場合には、さまざまなトラブルが起こる要因にもなりかねないため、測量士や土地家屋調査士などの専門家に依頼して、境界を確定させてから売却に手続きを進めましょう。ご自身で適切な判断ができない場合には、不動産会社などに相談しても良いでしょう。売主様の利益を最優先に考え、物件情報を囲い込まないオープンな売却サービスで、
「高値売却・早期売却」の実現を目指す私たちセンチュリー21クレドの
不動産売却サービスに、是非ともご期待ください。
川越市・坂戸市・鶴ヶ島市を中心に不動産売却査定、早期売却・高額買取をご提案致します。
※こちらの記事は2023年2月時点の記事になり今後法改正などにより変更になる可能性がございます。
「高値売却・早期売却」の実現を目指す私たちセンチュリー21クレドの
不動産売却サービスに、是非ともご期待ください。
川越市・坂戸市・鶴ヶ島市を中心に不動産売却査定、早期売却・高額買取をご提案致します。
※こちらの記事は2023年2月時点の記事になり今後法改正などにより変更になる可能性がございます。

- 平屋建ての不動産
- ガレージ付きの不動産
- 土地面積100坪以上
- 3000万円台の物件
- 2000万円台の物件
人気の条件から検索
- 個人情報の取扱いについて
- Copyright(C) クレド All Rights reserved.
- センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。

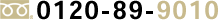



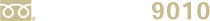 〒350-0233
〒350-0233